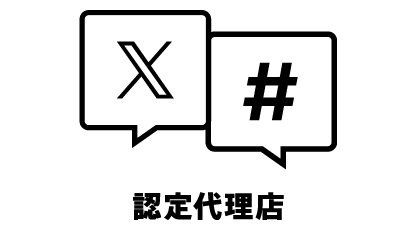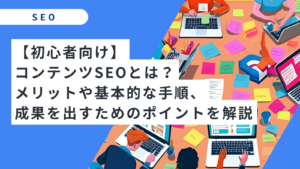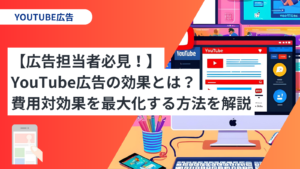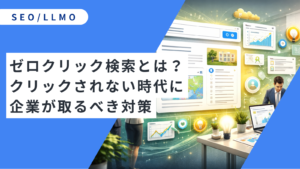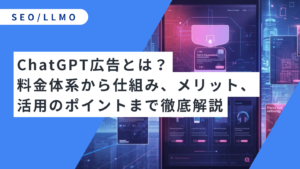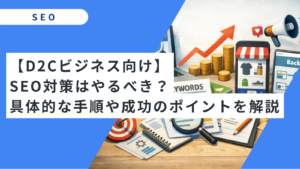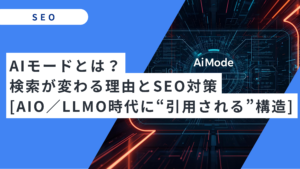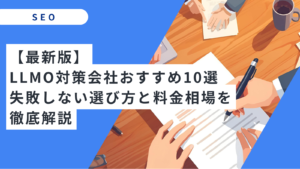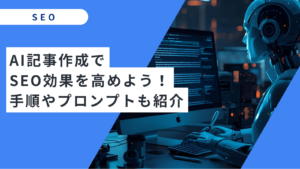【初心者向け】コンテンツSEOとは?メリットや基本的な手順、成果を出すためのポイントを解説
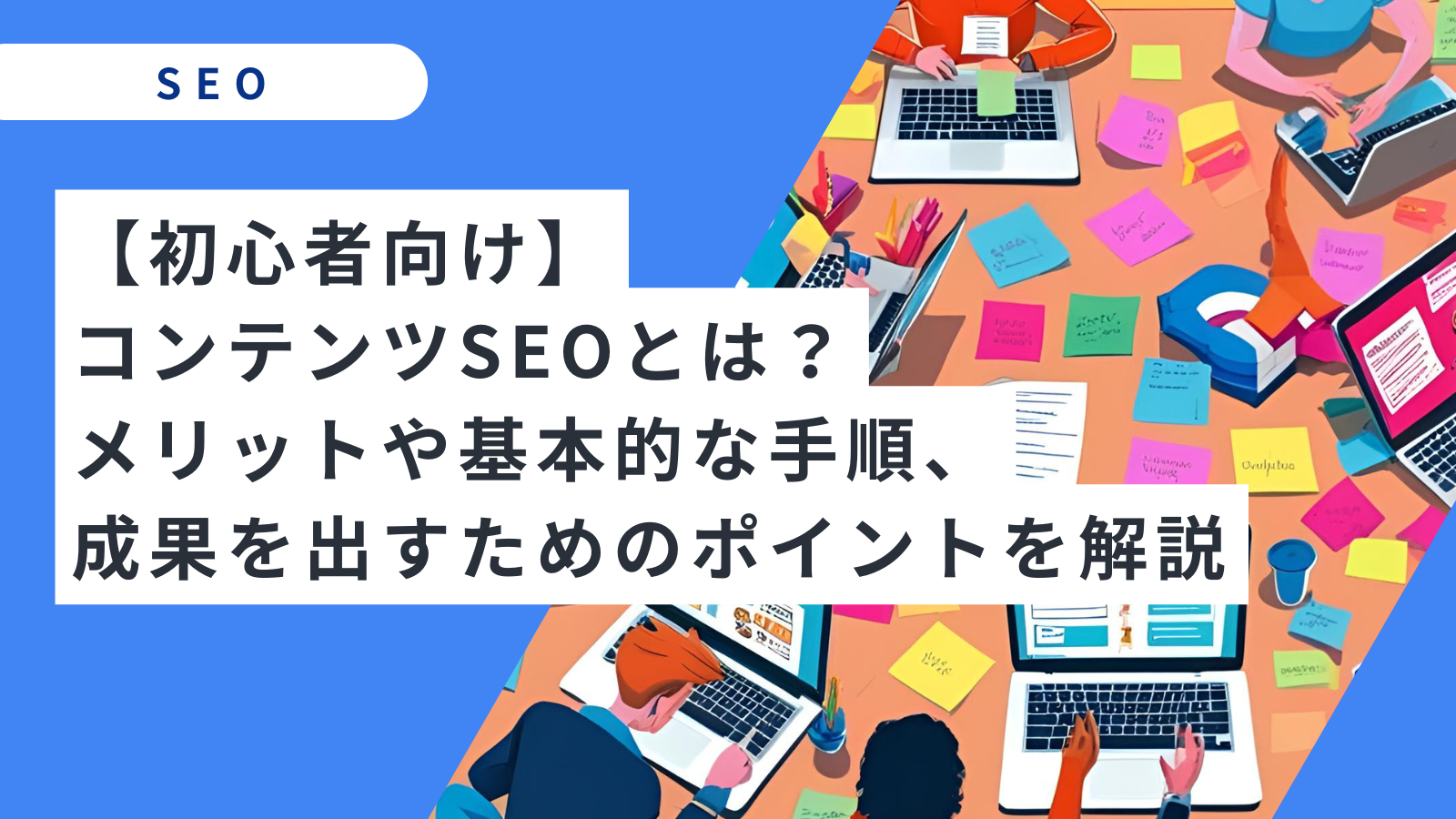
コンテンツSEOとは、ユーザーの検索意図に応じた良質な価値あるコンテンツを継続的にWebサイトやオウンドメディアで提供することで、検索エンジンからの評価を高めて自然検索からの流入を増やす方法です。
コンテンツSEOを実践することで、ユーザーの興味・関心を引き、中長期的な集客が見込めます。
本記事では、コンテンツSEOの概要と重視される理由、主なメリットを解説します。
コンテンツSEOとは?
コンテンツSEOとは、ユーザーの検索ニーズや意図に沿った高品質なコンテンツをWebサイトやオウンドメディアで継続的に発信し、自然検索からの流入を増やして集客効果を高めるSEO施策です。
ユーザーの関心や検索ニーズに合った正確な情報をコンテンツとして提供することで、検索結果の上位表示を狙います。
コンテンツSEOは、単体でも効果を発揮しますが、タグの最適化などの施策と組み合わせることで、SEO対策の効果をさらに高めることができます。
また、コンテンツ制作では、ユーザーの検索意図を理解し、関連するキーワードや共起語を適切に選定することが重要です。
さらに、PDCAを回しながら継続的に改善を行うことで、SEOの効果を最大化できます。
コンテンツSEOが重視される理由
コンテンツSEOが重視されている理由は、Googleにおける取り締まりの強化です。
従来、インターネット施策では、低品質のコンテンツに対して被リンクを大量に設置して表示順位を上げる、いわゆる「ブラックハットSEO」が蔓延していました。
これらの問題を解決するためにGoogleは検索エンジンのアルゴリズムを改善し、ペンギンアップデートやパンダアップデートなどを実施して、Webサイトのコンテンツの改善を図りました。
現在では、検索エンジンのアルゴリズムにかなう、ユーザーニーズに沿った良質なコンテンツの掲載により評価を高める「ホワイトハットSEO」が主流となっています。

コンテンツSEOのメリット
コンテンツSEOを実施する代表的なメリットは次の7つです。それぞれ具体的に解説します。
作成したコンテンツが資産になる
コンテンツは将来的に企業の資産となり、継続的な集客を生み出します。
Web広告は出稿期間中は集客効果がありますが、費用がかかり、掲載終了後は効果がなくなります。
一方、コンテンツは一度制作すれば長期的に活用でき、安定した流入を確保できます。
さらに、制作したコンテンツはホワイトペーパーやダウンロード資料、メルマガ配信などにも転用可能で、リード獲得にも活用できます。
自社や商品・サービスのブランディング効果がある
コンテンツSEOにより上位表示されると、ブランディングやPR効果も期待できます。
一般に、検索結果の上位にある情報は信頼性が高いと認識されやすいため、コンテンツの上位表示がブランド力向上につながります。
検索エンジンはユーザー行動を分析し、有益なコンテンツを上位表示する仕組みです。
そのため、長く閲覧されたり、定期的に訪問されたりするコンテンツはSEO効果が高まります。
ブランド力が確立すれば、成約率の向上やリピーターの増加につながり、口コミや評価がSNSで拡散される機会も増えていきます。
費用対効果(コストパフォーマンス)が高い集客が可能
コンテンツSEOは、長期的に見て費用対効果の高い集客手段です。
Web広告は即効性があるものの、掲載終了後は集客効果がなくなります。
一方、コンテンツSEOで上位表示されれば、継続的な効果検証とアップデートによって集客力を維持・向上できます。
コンテンツSEOの主なコストはサーバー代やドメイン維持費、分析ツールの利用料などです。
一方、Web広告は継続的な出稿費用がかかり、リスティング広告のようにクリックごとに課金される場合は、想定以上の費用が発生するリスクがあります。
このように、コンテンツSEOは限られた予算で集客力を高められる施策です。
長期的にコストを抑えながら集客を強化したい企業にとって、取り組むべきSEO施策といえます。
潜在層から顕在層まで幅広いユーザーにアプローチできる
コンテンツSEOでは、自らのニーズに気づいていない潜在層から、興味関心を具体的に認識しており購買行動に至りやすい顕在層まで、幅広いユーザーにアプローチが可能です。
それぞれの購買プロセスやニーズに応じたコンテンツを提供することで、ユーザーは価値を感じやすくなるからです。
コンテンツSEOで潜在顧客や見込み顧客のニーズ・状況に応じたコンテンツを配信し続ければWebサイト自体の評価もあがり、自然な形で接点を設けて購買行動へと移行できるでしょう。

中長期的な集客ができる
コンテンツSEOの実施は、中長期的な集客につながることもメリットです。
前述の通り、広告による集客は即効性がありますが、出稿を停止すると流入がとまり集客効果がなくなります。
一方で、コンテンツSEOによって上位表示に成功すれば、定期的に更新・改善し続けることで広告に依存せずに集客が可能になります。
また、作成されたコンテンツは自社の資産として蓄積されるため、継続的な集客が実現します。
新しい広告を出稿しなくても、コストを抑えて長期的な集客基盤を築けることは、コンテンツSEOのメリットといえるでしょう。
企業の権威性の向上につながる
コンテンツSEOを長期的に実施すると、権威性の向上につながります。
検索エンジンはユーザーの認知度や著名人の評価をもとに権威性を判断し、高い権威性を持つコンテンツは上位表示されやすくなります。
また、上位表示された記事はさらに評価され、適切なコンテンツを提供し続けることで権威性を高めることが可能です。
ただし、検索意図はトレンドや社会情勢によって変化するため、定期的なコンテンツの更新が重要です。
さらに、シェアや被リンクの増加によって信頼性や権威性が強化され、SEO効果が高まります。
広告費の削減効果がある
コンテンツSEOコストを抑えて安定した集客を目指す方は、広告運用からコンテンツSEOに切り替えていくことをおすすめします。
コンテンツSEOによって流入数の母数が増えれば、CV数も増加します。
結果的に、広告運用に頼らない集客の仕組みが構築されるため、広告費の削減効果が得られます。
コンテンツSEOに成功すれば、Webサイトやオウンドメディアからの長期的な集客が実現して、CV率を高めることが可能です。
コストを抑えて安定した集客を目指す方は、広告運用からコンテンツSEOに切り替えていくことをおすすめします。
コンテンツSEOの基本的な手順
ここからは、コンテンツSEOを行う基本的な手順を解説します。
6つのステップに分けて説明しますので、各ステップへの理解を深めて実践にお役立てください。
① SEO対策を行う目的を明確にする
コンテンツSEOの目的を明確にしましょう。
目的は、商品・サービスの販売、信頼関係の構築、資料請求や問い合わせの増加など、企業ごとに異なります。
まずは、自社の目的を明確にしましょう。
また、KGI(最終目標)とKPI(中間目標)を設定すると、効果検証がしやすくなります。
例えば、初期は記事数をKGIとし、長期運用ではキーワード順位や流入数、CV数などを指標にするとよいでしょう。
目標は数値で管理し、段階に応じたKPIを設定することが重要です。
高すぎる目標にこだわると成果につながりにくいため、無理のない設定を心がけましょう。

② ペルソナを設定する
ペルソナとは、自社にとっての理想的な顧客像を指します。
ターゲット層に含まれる具体的な人物像であり、ペルソナを明確に設定することで、ユーザーニーズを把握して効果的なコンテンツの作成に役立てられます。
ペルソナを設定する際は、次の情報を細かく設定して、実際に存在するような顧客像を作り上げましょう。
- 年齢
- 性別
- 職業
- 収入
- 業種
- 抱えている課題・ニーズ
- 情報収集の方法や頻度の高い購買行動の傾向 など
例えば、経営層をターゲットにする場合は、業界動向や企業における成長戦略に関するコンテンツを必要とすると検討できます。
一方で、現場のメディア運用担当者がターゲットの場合は、具体的なSEO対策の手法や運用に便利なツールの紹介、活用法などを含めたコンテンツを提供すると興味・関心の醸成につながります。
③ キーワードを選定する
コンテンツSEOでは、ユーザーニーズに合ったキーワードに加え、関連キーワードを適切に選定することが重要です。
検索ボリュームだけでなく、ペルソナの属性や行動傾向を考慮し、検索意図を含めてキーワードを精査しましょう。
検索ボリュームが少ない場合でも、潜在キーワードを洗い出し、見込み顧客との接点を増やすことが重要です。
特に、企業サイトのコラムやオウンドメディアの記事は、見込み顧客との重要な接点になります。
ユーザーニーズに合ったコンテンツを提供するために、適切なキーワード選定を行いましょう。
キーワード選定の際は、複数の単語を組み合わせたロングテールキーワードの活用も有効です。
メインキーワードの検索ボリュームが少なくても、ユーザーは具体的なニーズを持って検索するため、ロングテールキーワードを設定することで成約率の向上が期待できます。
④ 不足コンテンツを制作する
続いて、選定キーワードにもとづいたコンテンツを制作します。
既存記事ではコンテンツが不足する場合は、追加で制作しましょう。
なお、自社独自の視点や専門的な知見を含めたコンテンツを制作することで、競合他社との差異化を図れます。
例えば、購買意欲が高まっている状況のユーザーに向けては商品・サービスの紹介記事よりも、具体的に参考にできる導入事例やその業界に特化した活用法などを含めるのが有効です。
また、ペルソナをもとに検討し、見込み顧客が関心を持ちやすいコンテンツを提供すると、SEO効果を高めてブランド力の強化も図れます。
⑤ 効果検証を行う
SEO施策の実施後は、実際に効果が得られているのかの測定を行いましょう。
GoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソールなどの分析ツールを導入して、ユーザーの流入経路や流入が多いキーワード、ユーザーのサイト内での行動パターンなどを分析します。
このとき、流入数やCVだけでなく、問い合わせや資料請求などのアクションに至ったユーザー数も確認しておきましょう。
検証結果を活用すれば、流入数が多いキーワードへのコンテンツの制作やCV率が低いWebページの問題点を改善するなどの具体的な対策を行うことで、より高い成果を生み出せるでしょう。
⑥ 必要に応じてリライトする
コンテンツ記事は、効果検証の結果に基づいて、リライトを行います。
特に見込み顧客との接点創出につながるコンテンツは、3ヵ月ごとなど定期的にリライトを実施して、検索エンジンからの評価を維持させることが重要です。
なお、リライト時は特に次のポイントの改善を意識することをおすすめします。
- タイトル・ディスクリプションの修正
- 記事冒頭のリード文の最適化
- 見出しの改善
- 図や表の挿入 など
リライト時は、一部だけでなく、記事全体を見直して整合性が取れるように見直すことをおすすめします。

効果的なコンテンツを制作する際のポイント
コンテンツSEOに際して、効果的なコンテンツを制作する際は、以下のポイントを意識することで成果につなげられます。
ユーザーの検索ニーズを理解して、それを満たす内容にする
コンテンツSEOの主な目的は、ユーザーニーズに応じた有益で良質な情報を継続的に提供することで見込み顧客の興味・関心を引き、流入数を増やすことにあります。
そのため、ユーザーの検索意図やニーズを理解したうえで、それらを反映できるコンテンツを制作する必要があります。
例えば、教育向けコンテンツであれば、「〇〇(商品・サービス)の導入事例」「〇〇の活用方法」などのコンテンツを制作して、ユーザーに導入後のイメージを持ってもらい、購買意欲を高めていくのが有効です。
一方で、集客向けであれば「業界動向」「ユーザーの抱える課題解決に役立つコンテンツ」などが響きます。
目的を明確にしたうえでユーザーニーズを満たすコンテンツを制作すれば、SEO効果を高めることも可能です。
E-E-A-Tを意識した内容にする
E-E-A-Tに基づくコンテンツは、検索エンジンからの評価につながりやすい傾向にあります。
E-E-A-Tとは、 経験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trust)の頭文字を取ったものです。
| 経験(Experience) | 実体験や経験に基づく記事であること |
| 専門性(Expertise) | 特定の分野での信頼性や専門知識が掲載されたコンテンツであること |
| 権威性(Authoritativeness) | コンテンツのトピックの情報源として、 他のユーザーからどの程度認知されているか |
| 信頼性(Trust) | Webサイトや掲載コンテンツが信頼できるものであるか |
対策キーワードに対する主要タグ設定を最適化する
制作したコンテンツを検索エンジンに評価してもらうには、Webページの情報を正しく伝える必要があります。
そこで最適化したいのが、対策キーワードに対する主要タグです。
ここでは、タイトルタグとhタグの最適化について解説します。
タイトルタグ
タイトルタグとは、そのWebページがどのような内容であるかを検索エンジンに伝える役割を担うHTMLタグです。
検索エンジンは、タイトルタグを基準に、ユーザーが情報を検索した際に、検索意図に応じた正しいコンテンツが表示されるかを判断しています。
タイトルタグに設定した内容は、検索結果に表示されるため、必ず設定しましょう。
hタグ
hタグとは、Webサイトの見出しを検索エンジンに伝えるためのHTMLタグです。
hとは、heading、つまり「見出し」を意味します。
hタグにはh1〜h6までの種類があり、数字が大きいほど階層が深く、小さいほど階層が浅くなるのが特徴です。
h2のなかにh3を複数個設定する、h3の中にh4を設定するというように、構造的に設定します。
対策キーワードをhタグに含めると、その見出しの内容や対策キーワードとの関連性を検索エンジンに伝えられるため、評価の上昇につながります。
サイトの構造を伝える意味でも、hタグを適切に設定することが重要です。
適切に内部リンクを設置する
Webサイトの評価を上げるには、ユーザーがWebサイト内で最適な行動を取れるように内部リンクを適切に設置することも有効です。
関連コンテンツがあれば、その該当ページへの文字リンクやバナーを設置して、ユーザーを誘導できるようにしましょう。
関連ページへの内部リンクを適切に設置すると、ユーザーはWebサイト内で回遊できるため、滞在時間が延び、閲覧されるコンテンツも増加します。
結果として直帰率が下がり、CV数の増加も期待できるでしょう。
スマホユーザーに向けたコンテンツにする(モバイルファーストインデックス)
近年、パソコンだけでなくスマホなどのモバイル端末からアクセスするユーザーの数が増加しており、2018年には、Googleから「モバイル ファースト インデックスの展開」として、今後はスマホサイトを評価基準にすると公表されました。
モバイルファーストインデックスとは、モバイルからアクセスしているユーザーに快適な閲覧体験を提供できるコンテンツであることを検索順位を位置づける判断基準とする施策のことです。
そのため、コンテンツSEOの基本は押さえつつ、すべてのWebページをスマホ対応させて検索・閲覧しやすくすることが重要です。

定期的に内容を更新する(リライト)
コンテンツは制作して終わりではなく、定期的に効果を検証し、リライトを行いながら更新し続けることが重要です。
前述のように、3ヵ月ごとなどの定期的なリライトを行うことで、検索エンジンの評価を維持しやすくなります。
リライトの際は、タイトルやディスクリプション、見出しの見直しに加え、ユーザーが理解しやすいように図解を挿入するのも有効です。
また、本文を変更した際は、導入文も最適化し、記事全体の一貫性を保つことが大切です。
コンテンツを制作時に避けるべき行動
コンテンツSEOにおいては、ユーザーの検索意図に沿った有益な情報を制作・発信することが重要です。次にご紹介する行動は、検索エンジンからの評価を下げかねないため、意識的に避けるようにしましょう。
コピーコンテンツ(重複コンテンツ)を制作する
他のWebサイトのコンテンツをそのまま利用したり、少しだけ手を加えて公開したりするコピーコンテンツ(重複コンテンツ)は、Googleからの評価が下がるだけでなく、ペナルティにつながります。
あくまで、自社独自の経験や知見をもとに独自性のある記事を制作することが重要です。
ただし、必要に応じて他のWebサイトの情報や説明などを引用・参照しなければならないケースも生じます。
この時は、引用タグ(blockquote)を利用して、引用・参照していることを明確に記載しましょう。
関連性の低いサイトや質の低いサイトからの被リンクを獲得する
自社と関連性のないWebサイトや低品質なコンテンツからの被リンクは、検索順位の操作が対象と捉えられスパム判定につながります。
被リンクとは、別のWebサイトからのリンクを受けることで、過剰に行われるとペナルティの対象となります。
他にも、機械的に相互リンクを行うリンクファームの利用や有料リンクの購入と設置、自作自演のリンクも評価を下げる要因です。
本来の被リンクとは、自社のコンテンツが評価されて自然に他のWebサイトから紹介される状態です。
自然な被リンクを獲得するためには、他のWebサイトがリンクを行いたくなるような価値あるコンテンツを制作しましょう。
対策キーワードを過剰に詰め込み過ぎる
コンテンツSEOでは、ユーザーの検索意図に沿ったコンテンツを制作するため、キーワードの選定や記事への盛り込みが重要です。
さまざまなキーワードを多く盛り込むと、フックが増えて流入が増えるようにも感じますが、過剰に詰め込みすぎると不自然で読みにくい文章になってしまいます。
検索エンジンはユーザー行動や視点をもとにコンテンツを評価しているため、キーワードが不必要に使われていたり何度も出てきたりすると、評価が下がってしまうでしょう。
対策キーワードは自然に盛り込み、記事全体にバランスよく配置するように心がけましょう。
AIにて生成したコンテンツを編集せずに公開する
近年、生成AIの活用によって容易にコンテンツを制作できるようになりました。
しかし、一般的な生成AIは、Web上に散在する情報をもとにコンテンツが生成されるため、信ぴょう性や独自性に乏しくなります。
そのため、生成されたコンテンツ自体を編集せずに公開すると、コンテンツの価値が下がってしまい、検索エンジンからの評価が下がる可能性があります。
生成AIの活用は、アイデア出しなどにとどめるようにしましょう。
コンテンツSEOと併せて内部技術にも着手する
コンテンツSEOとあわせて、積極的に取り組みたいのが内部技術(テクニカルSEO)です。
検索エンジンに評価されるには、コンテンツだけでなく、Webサイトの構造も最適化する必要があります。
内部技術(テクニカルSEO)は、検索エンジンにコンテンツを適切に認識してもらうために欠かせない施策です。
例えば、サイトの階層構造の最適化、内部リンクやサイトマップの設置、表示速度の高速化、モバイル対応、タイトルや見出し・ディスクリプション、URLの最適化など、多岐にわたる施策があります。
コンテンツSEOは専門家に依頼するのも選択肢のひとつ!
コンテンツSEOは、自社のWebサイトやオウンドメディアへの流入を促す重要な施策です。
しかし、専門知識やスキルが求められるため、初めて取り組む場合は難しく感じることもあります。
その場合、SEO専門の代理店や制作会社に外注するのも有効な選択肢です。
外注することで、最新のアルゴリズムを反映した施策を実施でき、自社の業界に強い代理店なら、検索意図に沿った最適な戦略を立ててもらえます。
さらに、競合分析やサイト内部の最適化、キーワード選定などのサポートを受けられるため、効率的にSEOを進められます。
代理店を選ぶ際は、業界での実績、成功事例、予算などをしっかり見極めることが重要です。
まとめ:今すぐコンテンツSEOに取り組んでライバル企業に差をつける
コンテンツSEOは迅速に集客効果が見込める施策ではなく、検索エンジンに認識されて評価が高まるには一定の期間が必要です。
そのため、中長期的に取り組むことが必要であり、早い段階で着手することをおすすめします。
Lifunextでは、SEOコンサルティングとコンテンツ制作を組み合わせた、最適なSEO対策を提供しています。
コンテンツSEOに取り組みたいものの、何から始めれば良いのかわからない方は、お気軽にお問い合わせください。
株式会社LifunextのSEOコンサルティングサービスはこちら
Lifunextは大手SEO会社では実現できないレスポンスの速さや柔軟な対応力などベンチャーならではの質の高い小回りが利くプロフェッショナル集団です。
アップデート情報や業界トレンドなど独自情報もご提供できますのでお気軽にご相談ください。
無料のご相談・IT補助金を活用したプランがありますので、お気軽にお問い合せください。
\ SEO対策のご相談はLifunextへ /

早稲田大学卒業後、新卒でパーソルキャリア株式会社に入社。その後、個人事業主としてWEBメディアやYouTubeチャンネルの運営を行う。現在はLifunextのSEO事業部責任者としてBtoB、BtoCを問わず多くの企業を支援している。