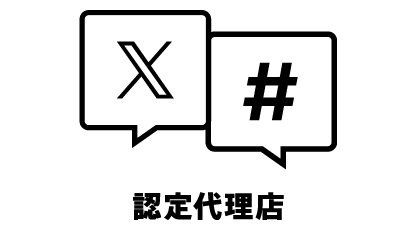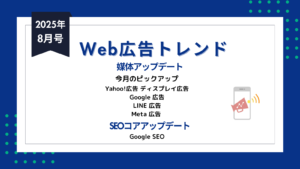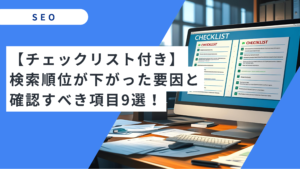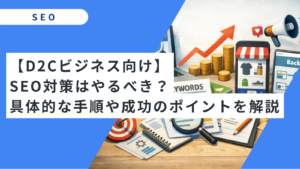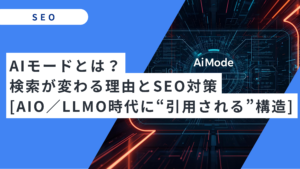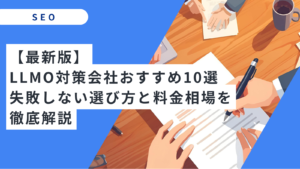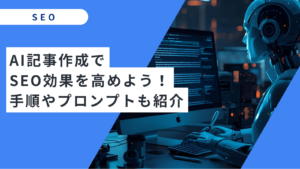【2025版】検索順位の上げ方徹底解説|内部・外部別SEO対策ポイント

SEOで検索順位を上げるためには、キーワード選定やコンテンツ制作といった施策に加えて、検索エンジンの仕組みを理解し、内部・外部の対策をバランスよく進めることが重要です。
本記事では、デジタルマーケティングの専門家であり、SEOでも豊富な実績を誇る株式会社Lifunextが、検索順位が決まる仕組みを整理したうえで、コンテンツ・テクニカル・被リンクといった具体的なSEO対策を体系的に解説します。
検索順位が上がらず悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
検索順位の決まり方とSEOの全体像
検索順位を上げるためには、検索エンジンがどのように情報を処理し、評価しているのかを理解することが重要です。
また、多岐にわたるSEO施策を体系的に把握し、自社サイトに必要な対策を見極める視点も欠かせません。
まずは、検索エンジンの基本的な仕組みと、SEO全体の構造を理解し、効果的な改善を行うための前提知識を身につけましょう。

検索エンジンは「クロール・インデックス・評価」で表示順位を決める
検索エンジンは、主に「クロール」「インデックス」「評価(ランキング)」の3つのステップを通じて、Webページの掲載順位を決定しています。
最初の「クロール」は、検索エンジンロボット(クローラー)がWeb上のページを巡回し、情報を取得するプロセスです。
Googleの場合は、「Googlebot」と呼ばれるクローラーが使用されており、インターネット上のリンクをたどりながら新しいページや更新された情報を見つけていきます。
次の「インデックス」は、クローラーが取得した情報を検索エンジン内で整理・保存する段階です。
HTML構造や画像、構造化データの内容をもとに、ページの内容や関連性が記録されます。
最後の「評価(ランキング)」では、検索クエリとの一致度や被リンクの質、コンテンツの専門性・信頼性など、さまざまな要素をもとに検索順位が決定されます。
Googleによれば、評価に用いられる要因は200以上あるとされています。
これらの検索順位を左右する要因に対して、内部・外部の両面から働きかけていくのが、SEO対策の本質です。
SEO施策は大きく「内部」「外部」の2軸
SEO施策は、大きく「内部施策(オンページ)」と「外部施策(オフページ)」に分けられます。
内部施策では、主にサイト内の構造やコンテンツを整えることで、検索エンジンから正しく評価される状態をつくります。
「コンテンツSEO」と「テクニカルSEO」の2つの側面があり、それぞれキーワード選定や記事構成、ページ表示速度やモバイル対応など、異なる観点からの対策が求められます。
一方、外部施策は、被リンクの獲得やSNSでの拡散などを通じて、検索エンジンからの信頼性を高めていくことが目的です。
検索順位を上げるには、特定の対策に偏らず、内部施策と外部施策の両面にバランスよく施策を進めることが大切です。
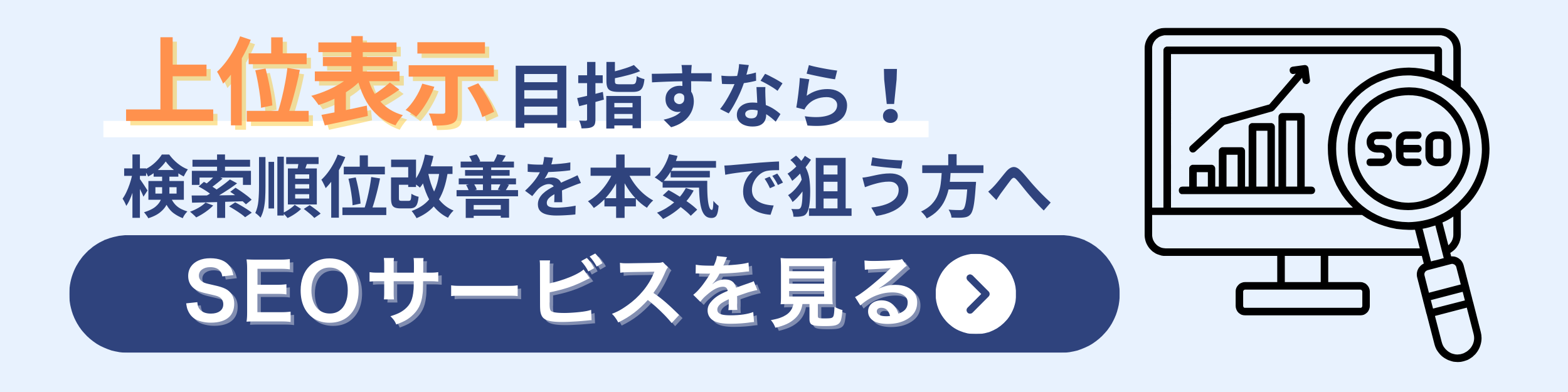
検索順位を上げるコンテンツSEO施策
検索順位を上げるには、検索エンジンだけでなく、ユーザーからも評価されるコンテンツづくりが重要です。
Googleはユーザーの利益を最優先に評価しており、どちらか一方に偏った対策では上位表示につながりません。
そこで必要なのが、両者に配慮したコンテンツSEOです。ここでは、質の高いコンテンツをつくるための4つのポイントを解説します。
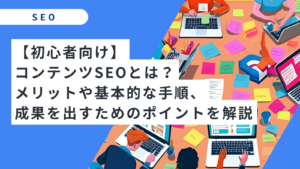
適切なキーワードの選定と自然な配置
SEO施策においては、検索意図に合致したキーワードを適切に選定し、自然な形でコンテンツ内に配置することが基本です。
まずは、メインキーワードを軸に、想定する検索ユーザーが入力しそうな語句(検索クエリ)を洗い出します。
そのなかから、検索ボリュームや競合性をふまえて、コンテンツ内で使用するキーワードを選定しましょう。
選定したキーワードは、タイトルや見出し、本文の冒頭、画像のalt属性など、読者にとって違和感のない位置に散りばめます。
あまりに詰め込みすぎると可読性が下がるだけでなく、検索エンジンからスパムと判断されるリスクもあるため、自然な文章の流れを意識することが重要です。
検索意図を満たす網羅的なコンテンツを作る
検索結果で上位に表示されるには、検索ユーザーの意図を的確に捉え、過不足のない情報を盛り込んだコンテンツを作成する必要があります。
「なぜこのキーワードで検索したのか」「どのような情報を求めているのか」を読み解き、構成全体でその意図に応える設計を意識しましょう。
主なトピックだけでなく、関連情報や補足的な内容も盛り込むことで、コンテンツの網羅性が高まります。
また、表や図、具体的な事例などを加えることで、理解しやすく、信頼性のある記事に仕上がります。

タイトル・見出しタグの最適化
タイトル(titleタグ)はそのページの主題を示す看板であり、検索結果上でのクリック率(CTR)にも影響します。
検索キーワードを自然に含めながら、ユーザーの興味を引く魅力的な表現を心がけましょう。
また、h2やh3などの見出しタグを適切に用いることで、ページの内容が階層的に整理され、検索エンジンに情報の構造が伝わりやすくなります。
読者にとっても、見出しを確認しただけでコンテンツの要点が把握できるような設計が理想的です。
定期的なリライト・情報更新をする
公開後のコンテンツは、時間の経過とともに情報が古くなったり、検索ニーズの変化によってユーザーの求める情報とズレが生じることがあります。
検索順位が上がらないと感じたときは、コンテンツの見直しを行いましょう。
特に、検索順位が落ちてきたページや、新たな検索ニーズが出現した場合は、内容を最新の情報に差し替えることで、再評価を得られる可能性があります。
なかでも、統計データやトレンドを含むコンテンツは定期的な更新が必要です。
改善の際はタイトルや見出し、リード文の表現だけでなく、情報の抜けや重複の有無など、記事全体の整合性を意識して見直すことが成果につながります。
検索エンジンに正しく評価されるためのテクニカルSEO施策
検索エンジンのクロールやインデックスを円滑にし、検索順位の底上げを狙うには技術的な施策が欠かせません。
ここでは、robots.txtやサイトマップ、内部リンクの整理、構造化データ、表示速度、モバイル対応など、テクニカルSEOの要点を解説します。

クローラビリティ最適化(robots.txt・サイトマップ・内部リンク)
検索エンジンにページを正しく評価してもらうためには、クローラーがサイト内をスムーズに移動できる状態を整えておくことが基本です。
たとえば、robots.txtでは不要なページのクロールを制限しつつ、重要なコンテンツへのクロールを妨げないよう設定しましょう。
また、XMLサイトマップを送信することで、サイト全体の構造を検索エンジンに正しく伝えることができます。
さらに、内部リンクを最適化することで、クローラーの回遊効率が高まり、ページ間の評価の伝達もよりスムーズになります。
内部リンクの最適化
ユーザーにも検索エンジンにも伝わりやすいサイト構造をつくるには、内部リンクの整理が欠かせません。
関連性の高いページ同士を自然な形で結び、わかりやすいアンカーテキストを設定することで、巡回性と回遊性の向上が期待できます。
重要ページにリンクを集める設計を行うと、評価の集約が進み、SEO上の効果も高まります。
ページの孤立を避け、すべてのコンテンツがつながる構造を目指しましょう。

構造化データとスニペット対策
FAQやレビュー、商品情報などに対応したスキーマを設定すれば、検索結果にリッチスニペットとして表示されやすくなり、視認性とクリック率の向上が期待できます。
Googleが推奨する構造化データの形式を活用し、コンテンツの内容を機械にも明確に伝えられるように整備しましょう。
ページスピードの改善(Core Web Vitals)
ページの表示速度はユーザー体験だけでなく、検索順位にも影響を与える重要な指標です。
特に「Largest Contentful Paint(LCP)」「Interaction to Next Paint(INP)」「Cumulative Layout Shift(CLS)」といったCore Web Vitalsの3項目は、Googleが公式に評価対象として挙げています。
画像の最適化や不要なスクリプトの削減、キャッシュの活用などを通じて、パフォーマンスの改善を図りましょう。
参考:Core Web Vitals と Google 検索の検索結果について|Google 検索セントラル
モバイルフレンドリー対応
モバイル端末からのアクセスが主流となった現在、モバイル対応は検索順位を左右する重要な要素です。
現在Googleではすべての評価をモバイル基準で行う「モバイルファーストインデックス」を採用しており、スマートフォンでも快適に閲覧できる設計が求められます。
レスポンシブデザインの導入や、タップしやすいリンク配置、読みやすいフォントサイズなどの調整を通じて、モバイルユーザーにもストレスのない設計を心がけましょう。

検索順位を支える外部施策
検索エンジンからの信頼や評価を高めるには、サイト外部からの支持が欠かせません。
3つの外部施策について、それぞれの役割と実践のポイントをご紹介します。
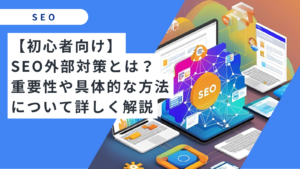
良質な被リンクの獲得とその基準
検索エンジンは、信頼できるサイトからのリンクを「推薦」として評価します。
そのため、関連性が高く、ドメインの信頼性もあるサイトからの被リンク獲得が重要です。
業界の専門サイトや権威あるメディア、著名人ブログなどからの引用は理想と言えます。
ただし、低品質なリンクやリンク購入による不自然な貼り方は逆にペナルティを招くリスクがあるため、獲得先の信頼性や獲得方法には注意を払いましょう。
自然リンクを増やすためには、オリジナルの調査データや優れたノウハウの公開が王道の方法です。
SNSやメディア露出による拡散を活用
自社コンテンツがSNSやニュースメディアで取り上げられると、一時的に大きなアクセスが発生するだけでなく、結果として外部リンクの獲得にもつながります。
拡散されやすいテーマ設定と、魅力的な見出し・ビジュアル設計が成果の鍵です。
リリース後の紹介活動や、投稿するタイミングの検討、ターゲットに届きやすい配信計画を練ることが大切です。
また、SNSからの流入が増えるとエンゲージメントも高まり、検索エンジンからの評価にもプラスになります。
サイテーションの重要性
サイトへのリンク以外に、ブランド名やサービス名が他サイトで言及(サイテーション)されるだけでもSEO上の評価に寄与します。
特に、「会社名+サービス」や「商品名+レビュー」など具体的な言及は、検索エンジンにとって信頼できる指標となります。
ネガティブな言及を避けるために、良質なPR活動やコミュニティでの丁寧な対応も不可欠です。

検索順位を下げるNG施策
検索順位を上げるつもりで行った施策が、かえって評価を下げてしまうこともあります。
ここでは、知らずに実行しやすいNG施策やスパム行為を整理し、避けるべきポイントを解説します。
内容によってはペナルティの対象となる場合もあるため、正しい知識が不可欠です。

AIコンテンツの量産・不自然な文章生成
生成AIを活用したコンテンツ制作が一般化するなか、品質管理されていないAIコンテンツの量産はSEO上のリスクとなります。
文脈に合わないキーワードの乱用や、機械的な文章の繰り返しは、ユーザー体験を損なうだけでなく、Googleから「価値のないコンテンツ」と判断されやすくなります。
AIを活用する場合でも、人の手による編集や監修を通じて、読みやすさや専門性を担保し、ユーザーにとって有益な内容に仕上げることが必要です。
不正リンク・過剰な相互リンク購入
外部リンクによる評価を高めようと、リンクの売買や過剰な相互リンクを行うことは、現在のGoogleのガイドラインに明確に違反します。
こうした手法は短期的に順位を押し上げる可能性がある一方、検出された場合は大きなペナルティを受けるリスクがあります。
検索エンジンはリンク元の信頼性や関連性を厳しくチェックしており、不自然なリンクは評価を下げる要因となります。
外部リンクの獲得は、あくまで自然な露出や引用によって獲得できるのが理想です。
低品質・重複コンテンツの公開
情報量が少ない記事や、他サイトと同一または類似したコンテンツを大量に公開することも、検索順位にマイナスの影響を与えます。
情報の独自性や網羅性が不足していると、検索エンジンからの評価が得られず、競合に順位を奪われるケースも少なくありません。
また、同一ドメイン内に似たような記事が並ぶと、インデックスの優先順位が分散し、自社サイト全体の評価が下がるおそれもあります。
常にユーザーの検索意図を意識し、独自性と価値のある内容を提供するよう心がけましょう。
検索エンジンからペナルティを受けやすい不正な手法
検索エンジンを欺くような施策は、アルゴリズムの進化により検出されやすくなっています。
たとえば、ユーザーには見えない文字をページに埋め込む「隠しテキスト」や、検索エンジン用とユーザー用で異なる内容を表示する「クローキング」などが該当します。
これらはGoogleのガイドラインで明確に禁止されており、実施した場合は手動ペナルティやインデックス除外といった重大な影響を受けることになります。
技術的な工夫を施す際にも、正しいSEOの範囲内で行うことが重要です。
SEO対策とあわせて知っておきたい“LLMO”とは?
検索エンジンからの流入を安定的に増やすには、SEO対策によりコンテンツの上位表示を狙うだけでなく、検索画面に表示される「AIによる概要(AI Overview)」への対応も視野に入れることが重要です。
注目されているのが、「LLMO(Large Language Model Optimization)」という新しい概念です。
LLMOはChatGPTやBing AI、Perplexityなどの生成AIに自社サイトの情報を引用・参照してもらうための施策です。
現在、多くのユーザーが生成AIに直接質問して情報を得るなか、その回答の情報源に自社のWebサイトが利用されれば、間接的な信頼獲得や流入のきっかけを作ることができます。
具体的な対策としては、構造化データの整備や一次情報の発信、FAQ形式のコンテンツの充実などが効果的です。
LLMOは従来のSEOとも親和性が高く、他社との差別化にもつながる分野といえるでしょう。
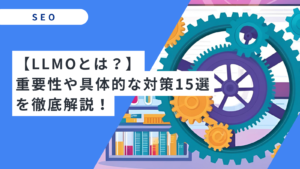

検索順位を上げるうえでのよくある質問【Q&A】
ここでは、検索順位を上げるための施策に関するよくある質問にお答えします。
不安や疑問を解消し、安心してSEOに取り組みましょう。
順位が上がるまでにどれくらいの期間がかかる?
SEOはすぐに効果が出る施策ではなく、ある程度の時間をかけて成果が現れるものです。
一般的には、記事を公開してから検索順位に反映されるまでに1〜3ヶ月程度かかると言われています。
ただし、競合の強さやドメインの信頼性、サイト全体の構成によっても変動するため、「何を」「どのくらい」「どの順番で」対策するかによって期間は大きく異なります。
新しいドメインや立ち上げ初期のサイトであれば、半年以上かかるケースもあるため、中長期的な視点で取り組むことが大切です。
リスティング広告は検索順位に影響する?
Google広告などのリスティング広告を出稿しても、検索順位(自然検索の順位)には直接的な影響はありません。
広告と自然検索の評価は別で管理されており、広告によってSEOのスコアが上がることはない仕組みになっています。
ただし、広告経由でコンテンツが多く読まれることで、結果的に被リンクが得られたり、指名検索が増えたりといった間接的な影響が出る可能性はあります。
とはいえ、リスティング広告は別の集客チャネルとして活用し、SEOとは切り離して考えるのが基本です。
順位チェックには何を使えばいい?
検索順位の変動を正しく把握するには、順位チェックツールの導入が有効です。
「GRC」「Rank Tracker」「ahrefs」「SE Ranking」などのツールは、あらかじめ登録したキーワードの順位を定期的に計測してくれます。
無料で使えるGoogleサーチコンソールでも、ある程度の順位推移は確認できますが、詳細な分析やキーワードごとの比較には専用ツールのほうが向いています。
精度や機能、使いやすさを比較しながら、自社に合ったツールを選びましょう。
まとめ|検索順位の決まり方とポイントをおさえて成果を出そう
なかなか検索順位が上がらない時期が続くと、不安になるかもしれません。
しかし、検索順位を上げるためには、テクニックだけに頼るのではなく、検索エンジンとユーザーの双方にとって価値のあるサイトを丁寧に育てていく姿勢が大切です。
小手先のテクニックに頼るよりも、基本に沿った対策を積み重ねることが、長期的な成果につながります。
まずは自社サイトの状態を客観的に見直し、できることから着実に取り組んでいきましょう。
検索順位の改善に向けて、SEO施策を本格的に進めたいとお考えの方は、ぜひLifunextへのご相談もご検討ください。
Lifunextでは、内部対策の最適化とコンテンツ制作を組み合わせたSEO支援を行っており、貴社の状況に応じたご提案が可能です。
株式会社LifunextのSEOコンサルティングサービスはこちら
Lifunextは大手SEO会社では実現できないレスポンスの速さや柔軟な対応力などベンチャーならではの質の高い小回りが利くプロフェッショナル集団です。
アップデート情報や業界トレンドなど独自情報もご提供できますのでお気軽にご相談ください。
無料のご相談・IT補助金を活用したプランがありますので、お気軽にお問い合せください。
\ SEO対策のご相談はLifunextへ /

早稲田大学卒業後、新卒でパーソルキャリア株式会社に入社。その後、個人事業主としてWEBメディアやYouTubeチャンネルの運営を行う。現在はLifunextのSEO事業部責任者としてBtoB、BtoCを問わず多くの企業を支援している。