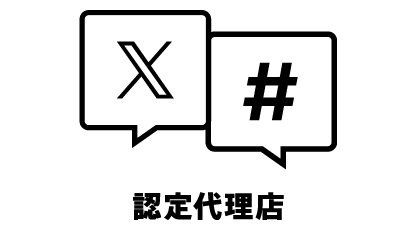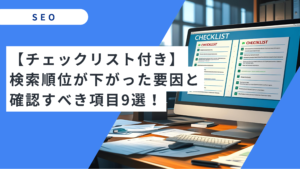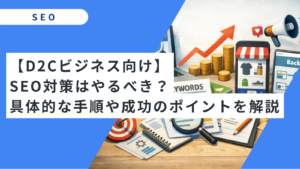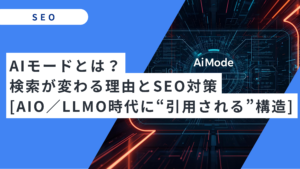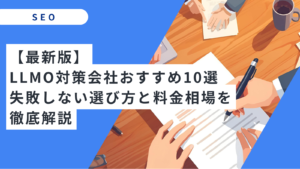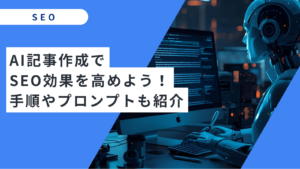【チェックリスト付き】検索順位が下がった要因と確認すべき項目9選!
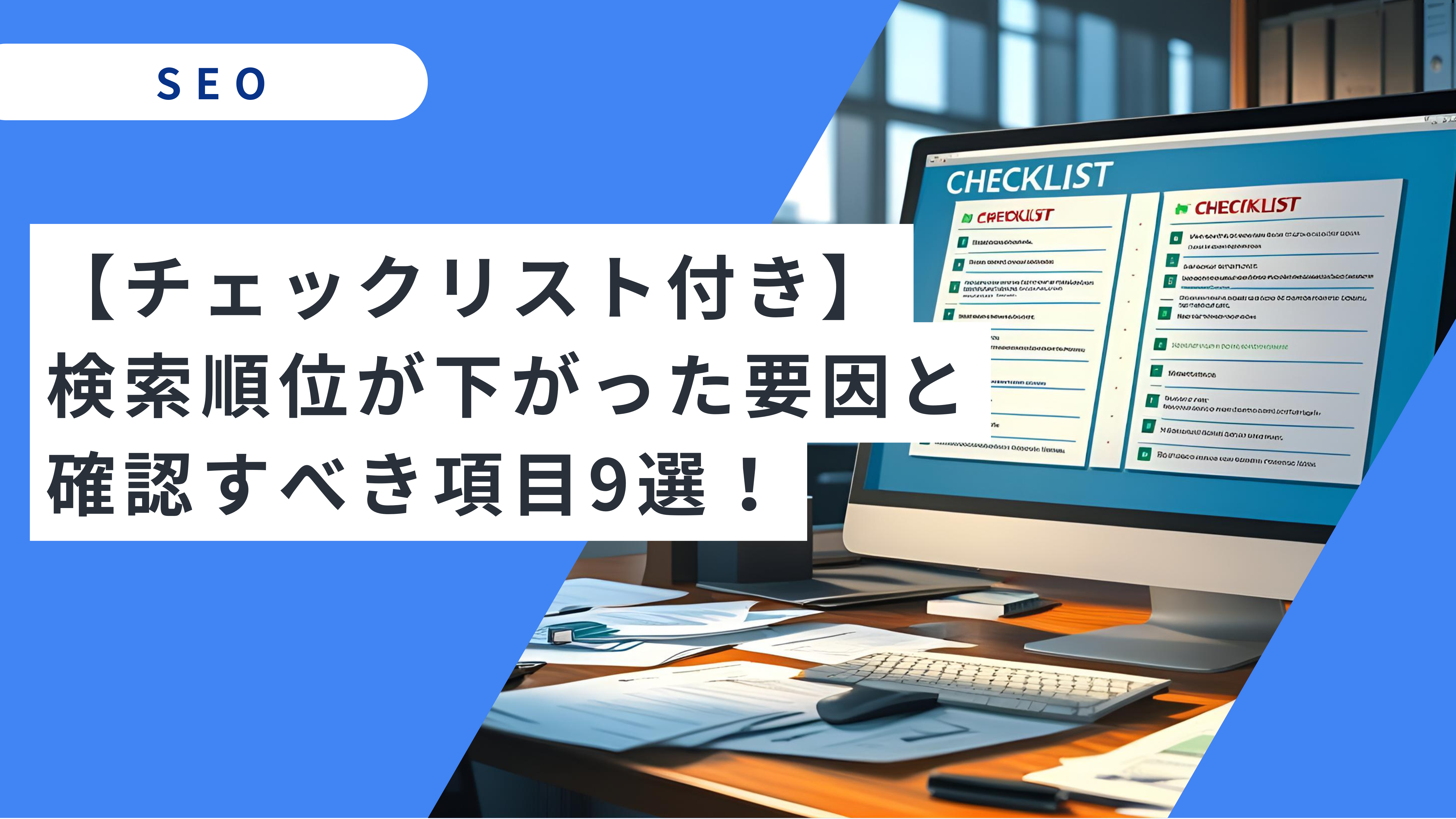
検索順位が下がっても、冷静に原因を特定し、適切な対策を講じれば回復は十分に可能です。
本記事では、デジタルマーケティングの専門家である株式会社Lifunextのノウハウを生かして、自社サイト・競合・Googleアップデートなど複数の観点から順位低下の要因を整理し、確認すべきポイントや改善策をわかりやすく解説します。
検索順位の維持・改善にお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。
Google検索順位が下がったときに考えられる要因
Googleの検索順位が下がった場合、原因は自社サイトだけでなく、競合の動きやGoogleの仕様変更など、外部要因にあることも少なくありません。
ここでは、検索順位に影響する3つの要素について、順に解説します。
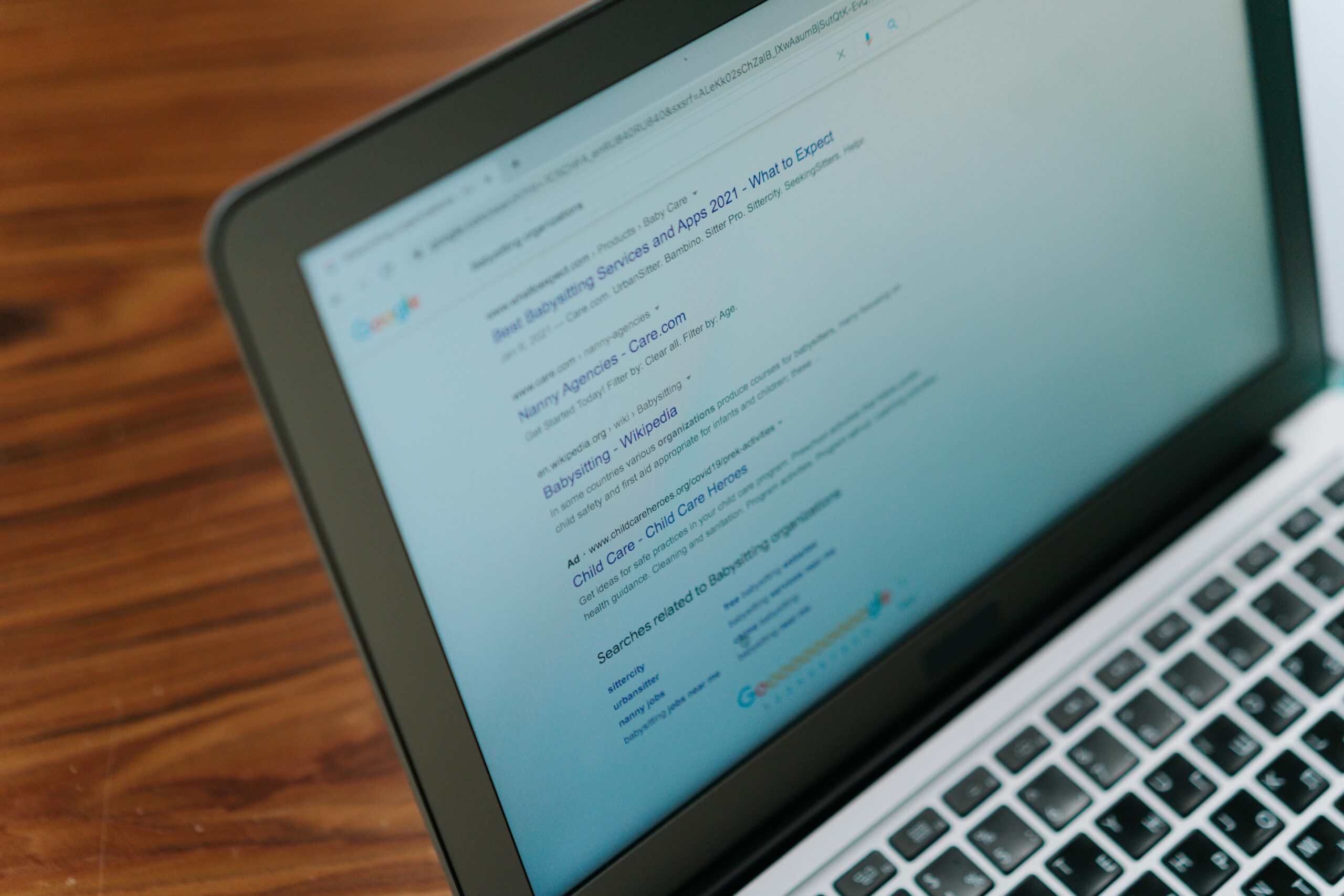
自社サイトによるもの
記事の内容が古くなっていたり、ユーザーの検索意図とのズレが生じていたりとコンテンツ自体に問題があると、Googleからの評価が下がる可能性があります。
画像のalt属性の設定漏れや内部リンク切れ、モバイル表示の崩れといった細かな技術的ミスも、検索順位に影響を与える要素のひとつです。
加えて、Googleのガイドラインに違反していると判断される場合は、手動ペナルティやアルゴリズムによる評価低下が発生することもあります。
コンテンツの盗用、過剰なキーワード使用、ユーザーにとって価値のないページの量産などが該当します。
競合サイトによるもの
検索順位は相対的に決まるため、同じキーワードでより優れたコンテンツを持つ競合サイトが現れると、自社サイトの順位が押し下げられることがあります。
特に、ドメインパワーの高い大手メディアや、大規模なSEO施策を行っている企業サイトが参入した場合は、その影響を受けやすくなります。
Googleのアルゴリズムによるもの
Googleは検索体験の向上を目的に、検索アルゴリズムのアップデートを定期的に行っています。
なかでも「コアアルゴリズムアップデート」が実施された際は、サイト構成やコンテンツ品質に問題がなくても、大きく順位が変動することがあります。
Googleはアルゴリズムの詳細を公表していないため、すぐに原因の特定や対策ができるとは限りません。
まずは全体的な傾向を把握し、検索意図や評価基準の変化を見極めたうえで、冷静に対応していくことが大切です。

【チェックリスト】検索順位が下がったら確認すべき項目9つ
検索順位が下がったときは、複数の要素を多角的に確認することが重要です。
以下では、「自社サイト」「競合」「Googleのアルゴリズム」の3つの観点から、特にチェックしておきたい9つのポイントを紹介します。
【自社サイトによるもの】Googleからのペナルティを受けていないか
コピーコンテンツの掲載、隠しテキスト、不自然な被リンクの操作など、Googleのガイドラインに違反すると、検索順位に大きな影響が出ることがあります。
違反行為がGoogleの担当者に認識された場合には、手動ペナルティが課されます。
この場合は通知が届くため、Search Consoleの「手動による対策」レポートで確認が可能です。
一方、通知がなくても、アルゴリズムによって自動的に評価が下がるケースもあります。
これまで順位が安定していたコンテンツが急落した場合は、ペナルティの可能性を疑い、自社コンテンツとGoogleのガイドラインを照らし合わせてみましょう。
【自社サイトによるもの】インデックスは外れていないか
検索順位が突然消失した場合、ページがGoogleにインデックスされていない可能性があります。
Search Consoleで「URL検査」を行い、「URLがGoogleに登録されていません」と表示される場合は、noindexの指定やクロールエラーが原因かもしれません。
また、robots.txtでのブロックやcanonicalの誤設定が影響することも想定されます。
インデックスされるべきページに問題がないかどうか、metaタグや構造を確認し、必要に応じて再インデックスをリクエストしましょう。
【自社サイトによるもの】競合サイトと比較して、記事品質は低くないか
順位低下の背景には、コンテンツの質が競合より劣っている可能性もあります。
ユーザーの検索意図に合致しているか、情報が十分に網羅されているか、最新の内容が反映されているかなどを見直してみましょう。
また、信頼性(引用・出典の明示)や読みやすさ、独自性も重要な評価要素です。
同じキーワードで上位表示されている競合記事と比較し、自社記事の改善点を洗い出すことで、リライトの方向性が明確になります。

【自社サイトによるもの】
関連性が低いサイトや悪質なサイトからの被リンクが多くないか
被リンクは本来、検索順位を高める要因ですが、リンクの質によっては逆効果になることがあります。
スパムサイトや無関係な海外のサイトからのリンクが大量にある場合、不自然なリンク操作と判断され、Googleからの評価が下がる可能性があります。
Search Consoleの「リンク」レポートを確認し、関係性の低い被リンクが目立つ場合は、リンク元の精査と必要に応じた「リンクの否認(Disavow)」を行いましょう。
ただし、通常のスパムリンクはGoogleが自動で無視する設計になっているため、無理に否認する必要はありません。
【自社サイトによるもの】記事のカニバリ(重複)が生じていないか
同一または類似するキーワードを含む記事が複数ある場合、Googleがどの記事を評価すべきか判断できず、結果的に全体の順位が下がる「カニバリ(カニバリゼーション:共食いの意)」が発生します。
カニバリはSEO対策に注力する企業でも陥りやすい落とし穴のひとつです。
対策として、該当記事の統合やリライトによる差別化、canonicalタグの適切な活用などがあります。
記事数が多いサイトを運営する場合は、定期的なコンテンツの棚卸しと整理が必要です。
【自社サイトによるもの】内部技術面(テクニカルSEO)において致命的な問題はないか
サイトの構造や表示速度、モバイル対応といった技術面も、順位に大きく影響します。
たとえば、Core Web Vitals(ページの読み込み速度や表示の安定性など)が低いと、ユーザー体験が悪化し、評価が下がる原因になります。
ほかにも、構造化データのエラー、クローラビリティの不備、内部リンク切れなど、技術的な問題が見落とされがちなため、定期的な確認が必要です。
積極的にSearch ConsoleやPageSpeed Insightsを使って、客観的なデータに基づいた改善を行いましょう。

【競合サイトによるもの】ドメインパワーが強い競合サイトが参入してきていないか
これまで安定して上位表示されていたキーワードでも、より強力なドメインを持つ競合サイトが参入してきた場合、順位が押し下げられることがあります。
特に、企業の公式サイトや大手メディア、業界特化型のポータルサイトなどは、信頼性が高く、コンテンツの質を伴えば短期間で上位に表示されるケースもあります。
自社の順位変動が起きた時期と、競合の新規記事公開のタイミングが重なっていないかどうかを確認しましょう。
また、競合のコンテンツ構成や情報の網羅性、独自性などを分析することで、自社コンテンツに足りない要素が見えてくる場合もあります。
SEOは「相対評価」であるという前提を忘れず、継続的なリライトと差別化の意識が重要です。
【Googleのアルゴリズムによるもの】
Googleコアアルゴリズムアップデートの発表がされているか

Googleは年に数回、大規模な「コアアルゴリズムアップデート(Core Algorithm Update)」を実施しています。
このアップデートでは、検索全体の品質評価基準の見直しが行われるため、検索順位が大きく揺れることも珍しくありません。
順位が大幅に下がったタイミングと、Google公式によるアップデートの時期が一致しているかを確認してみましょう。
情報源としては、Google Search Central BlogやSEO系ニュースサイトが有用です。
ただし、コアアップデートによる順位変動は、新しい評価基準に基づく再評価の結果であり、必ずしもコンテンツの質が悪いとは限りません。
順位が下がったからといって、むやみに全記事を修正することは避けましょう。
まずはどのようなコンテンツが評価されているかを把握し、対応の方向性を検討することが大切です。
参考:Google 検索のコアアップデートとウェブサイト|Google 検索セントラル
【Googleのアルゴリズムによるもの】
上位表示されているページの傾向が変わっていないか
Google検索における評価基準は、ユーザー体験の向上を目的として、日々見直されています。
それに伴い、上位表示されるページの傾向も年々変化してきました。
たとえば以前は網羅性の高い長文コンテンツが評価されていたのに対し、現在はシンプルでFAQ型の構成が好まれる傾向にあります。
検索結果に表示される10位以内のページを複数チェックし、内容の深さ・見出し構成・専門性の有無・媒体のタイプ(個人・企業・公式など)などを観察してみましょう。
また、最近はE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)に基づく評価が重視されており、実体験に基づいた記述や、執筆者の明示といった要素も順位に影響します。
上位サイトの構成やトーン、視点の違いを分析することで、自社の改善ポイントが明確になるでしょう。
確認が難しい場合は、SEOの専門家の力を借りるのも有効です。
自社サイト・競合サイト・Googleアルゴリズムの3つの観点から総合的にチェックすることで、順位低下の原因を正確に把握できます。
Lifunextでは、こうした分析を踏まえて、必要なリライト・構成改善・E-E-A-Tの強化など、実行フェーズまで一貫してサポートしています。
株式会社LifunextのSEO対策サービスについて詳しく見てみる>
検索順位が下がった原因の調査4ステップ
検索順位が下がったと感じたときは、焦ってリライトや修正を行う前に、原因を正しく特定することが重要です。
ここでは、順位低下の原因を特定するための4つの調査ステップを紹介します。

①.表示順位の変化を確認する
順位を落としたページのキーワードを正確に把握しましょう。
表示回数・クリック数・平均掲載順位はSearch Consoleの「検索パフォーマンス」から確認可能です。
過去7日・28日・3カ月など、異なる期間で比較することで、変化が顕著なページやキーワードが洗い出せます。
影響が出ている範囲を調べることも重要です。
複数のページに共通して影響が出ているのか、特定のジャンルやカテゴリに限定されているのかを調査することで、問題の範囲を切り分けるヒントになります。
検索順位チェックツールを併用すると、より詳細な変動を追いやすくなるため、検討してみましょう。
②.自社サイトの内部に問題がないか確認する
技術的な不具合やインデックス状況の確認を行いましょう。
Search Consoleの「URL検査ツール」を活用し、該当ページがGoogleに正しくインデックスされているか、クロールエラーが起きていないかどうかを確認します。
また、metaタグのnoindex設定やcanonicalタグの誤用、robots.txtによるクロール制限にも注意が必要です。
さらに、モバイルフレンドリーの対応状況やページスピードの低下も、検索順位に影響することがあります。
PageSpeed Insightsなどの無料ツールも活用しながら、内部構造を広く点検しましょう。
③.自社コンテンツの品質を確認する
情報が古くなっていないか、検索ユーザーの意図にきちんと応えているか、他サイトに比べて内容の網羅性や独自性があるか、コンテンツの中身を確認しましょう。
なかでも検索意図とのズレは見落とされがちです。
たとえば、「◯◯とは」というキーワードの場合、情報提供型の記事が求められているにも関わらず、自社商品の訴求中心になっている場合など、意図と形式のミスマッチが発生していることがあります。
また、誤字脱字や見出し構成の乱れ、専門性や信頼性の欠如も、品質低下の要因です。
上位表示されている競合記事と見比べながら、読み手視点での改善点を探しましょう。
④.外的要因を確認する
サイト内に明確な問題が見つからない場合は、外的要因の可能性を探ってみましょう。
まず、Googleのコアアルゴリズムアップデートが行われていないかを確認します。
アップデートのタイミングは、公式ブログや業界ニュースメディアで発表されることが多いため、確認が可能です。
順位が下落した時期と一致していれば、影響を受けた可能性があります。
また、ドメインパワーの高い競合サイトが同じキーワードに参入していないかどうかも重要な観点です。
そのほか、低品質な被リンクの急増や、SNSやニュースでのネガティブな言及によってGoogleの評価が変わることもあります。
内部要因で説明がつかない場合は、こうした外的要因を広く見渡すことがポイントです。
外的要因まで調査しても明確な原因がつかめない場合は、専門家の力を借りるのも有効です。
自社だけでの調査が難しいケースも多いため、SEO会社に外注するという選択肢も検討してみましょう。
Lifunextでは、検索順位が下がった要因を丁寧に分析したうえで、適切なリライトや構造改善、コンテンツ強化まで一貫してサポートしています。
また、毎月5社限定で、SEOの無料診断も行っていますので、ぜひご活用ください。
下がった順位を回復させるための対策とは
順位が下がった原因を特定できたら、次は改善に向けた具体的な施策に着手する必要があります。
ここでは、特に効果が高い4つのアプローチを紹介します。

コンテンツの新規作成・リライトを行う
順位回復のためには、まず既存コンテンツのリライトから取り組むのが基本です。
情報が古くなっていたり、検索意図とのズレがある記事はユーザーにとって価値が低いと判断され、順位が下がる原因となります。
そのため、最新のデータや統計の反映や、ユーザーの疑問に対するFAQ追加などを通じて、記事の信頼性と利便性を高めましょう。
また、単に既存記事の内容を拡張するのではなく、新たな視点や検索ニーズに対応した別記事を作成することで、サイト全体の網羅性が高まり、評価が向上するケースもあります。
競合の構成や上位表示コンテンツの傾向を参考に、ユーザーが求める情報を的確に届けるコンテンツ制作を心がけましょう。
内部技術課題(テクニカルSEO)を改善する
コンテンツが良くても、サイトの構造や技術的な問題によって、Googleに正しく評価されないケースもあります。
たとえば、読み込み速度の低下、モバイル非対応、JavaScriptによる表示遅延などは、ユーザー体験だけでなくSEOにも影響します。
Search Consoleのエラー項目や、PageSpeed Insights、Lighthouseなどのツールを活用し、サイトのパフォーマンスを客観的に評価しましょう。
また、内部リンクの最適化やパンくずリストの設定、構造化データの整備などの見直しも効果的です。
細かな改善を積み重ねていけば、検索エンジンとユーザーの双方からより高い評価を得られるでしょう。
外部対策を実施する
外部対策(オフページSEO)とは、被リンクの獲得やSNSによる言及など、自社サイト外からの評価を高める施策を指します。
なかでも被リンクは、Googleにとって「他者からの推薦」にあたる重要なシグナルです。
質の高い外部サイトからのリンクを得ることで、自社サイトの信頼性や権威性が向上し、検索順位に好影響を与えられます。
とはいえ、被リンクは自然に獲得するのが理想的です。
無理な相互リンクやリンクの購入など、不自然な対策は逆効果になるおそれがあります。
プレスリリースの配信や業界メディアへの寄稿、SNSや動画との連携など、効果的に自社コンテンツを外部に広げる工夫を取り入れましょう。
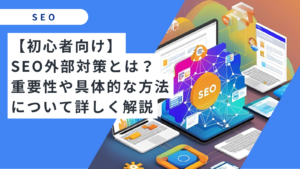
UI・UXを改善する

検索エンジンは、ユーザーの体験(UX)も重要な評価指標として扱っています。
たとえば、ページの滞在時間が極端に短かったり、直帰率が高かったりする場合、ユーザーにとって価値の低いコンテンツと判断される可能性があります。
改善策としては、読みやすい文字サイズや行間の調整、視覚的に整理されたレイアウト、スマホでも快適に操作できる設計などが挙げられます。
また、ページ内リンクやCTAボタンの設置位置もポイントです。
ユーザーが迷わずスムーズに目的を達成できる設計に見直すことで、Googleからの評価向上にもつながります。
検索順位の上げ方については、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

順位回復対策に伴う注意点
検索順位が下がると、焦ってさまざまな手を打ちたくなるものですが、原因を正しく把握せずに対策を行ってしまうと、かえって状況を悪化させるおそれもあります。
ここでは、順位回復に向けて取り組む際に押さえておきたい2つの注意点を解説します。
まずは順位低下の原因を特定する
順位が落ちたからといって、すぐにコンテンツを大幅に書き換えたり、リンクを否認したりするのはリスクがあります。
適切な対策を講じるためには、下がった原因を明確にすることが不可欠です。
Search Consoleでのインデックス状況やエラーの有無、上位サイトとの差異、アルゴリズムアップデートの影響など、複数の観点から丁寧に分析を行いましょう。
原因を取り違えたまま施策を進めると、さらなる順位低下を招いてしまう可能性もあるため、冷静な調査が必要です。
短期的な成果を求めすぎない
SEOは即効性のある施策ではありません。どれほど適切な対応を行ったとしても、Googleの評価に反映されるまでには一定の時間がかかります。
特に、コアアルゴリズムアップデートの影響を受けた場合は、次回のアップデートまで評価が戻らないケースも珍しくありません。
順位が回復するまでの期間は、ユーザー体験の向上や新たなコンテンツの充実、技術的な改善など、中長期的な観点でできることに取り組むことが大切です。
「すぐに戻らない=失敗」と捉えず、継続的に改善を続けていきましょう。
検索順位が下がったらLifunextに相談しよう!
検索順位の低下に対して、自社でできる対応には限りがあります。
原因が複雑で判断が難しい場合や、改善施策を実行するリソースが足りない場合は、専門家に相談するのも有効な選択肢です。
SEOのプロは、検索エンジンのアルゴリズムの変化や評価基準に関する最新の知見を持っており、構造的な問題や競合分析を通じて、より的確な施策を提案できます。
また、自社サイトの強みや課題に応じて、テクニカルSEO・コンテンツSEO・外部対策といった多角的な視点からアプローチできるのも強みです。
検索順位の改善に向けて、SEO施策を本格的に進めたいとお考えの方は、ぜひLifunextへのご相談もご検討ください。
Lifunextでは、内部対策の最適化とコンテンツ制作を組み合わせたSEO支援を行っており、貴社の状況に応じたご提案が可能です。
また、毎月5社限定で、SEOの無料診断も行っていますので、ぜひご活用ください。
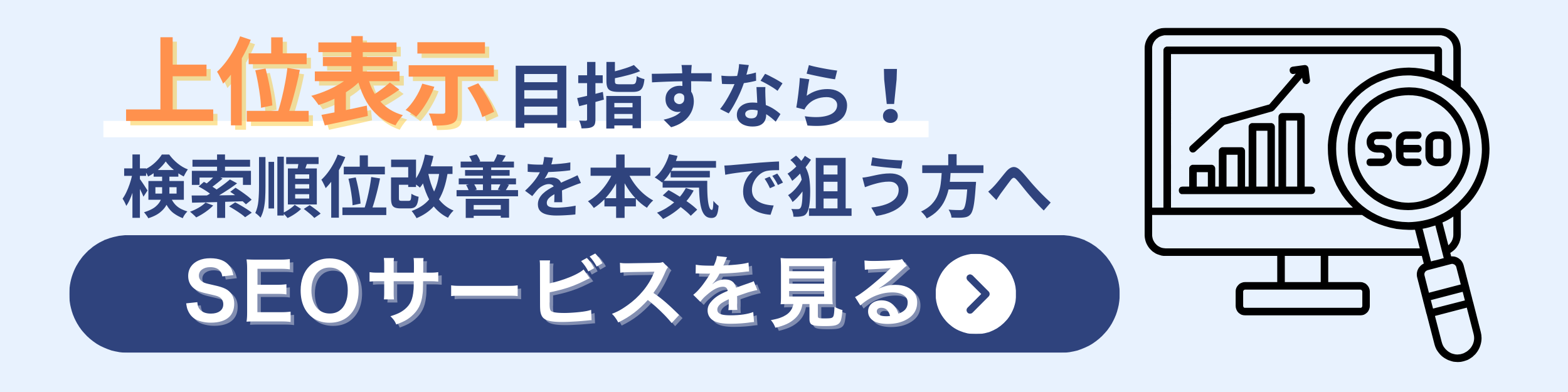
まとめ|順位低下は全体を見直すチャンス!
検索順位の変動は、どのサイトにも起こり得る現象です。
検索順位が下がったときこそ、自社サイトの状態や競合の動向、Googleの評価基準を見直す良い機会といえるでしょう。
今回紹介したチェックリストや調査ステップをもとに、まずは冷静に原因を分析しましょう。
コンテンツの質やユーザー体験の向上を意識しながら、内部・外部の両面から継続的に改善を重ねていけば、長期的な成果が期待できます。
必要に応じて専門家の力を借りるのも有効な選択肢です。
株式会社LifunextのSEOコンサルティングサービスはこちら
Lifunextは大手SEO会社では実現できないレスポンスの速さや柔軟な対応力などベンチャーならではの質の高い小回りが利くプロフェッショナル集団です。
アップデート情報や業界トレンドなど独自情報もご提供できますのでお気軽にご相談ください。
無料のご相談・IT補助金を活用したプランがありますので、お気軽にお問い合せください。
\ SEO対策のご相談はLifunextへ /

早稲田大学卒業後、新卒でパーソルキャリア株式会社に入社。その後、個人事業主としてWEBメディアやYouTubeチャンネルの運営を行う。現在はLifunextのSEO事業部責任者としてBtoB、BtoCを問わず多くの企業を支援している。